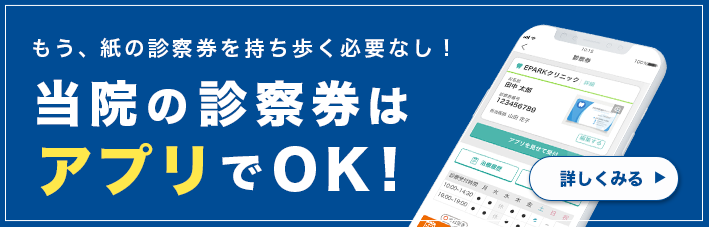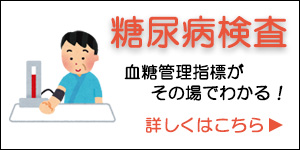臨床医として伝えたいこと ― 100年時代を生きるあなたへ ―
医療の進歩は日々目覚ましく、循環器領域においても、かつては治療困難とされた病気に対して有効な薬剤やデバイスが次々と登場しています。高血圧や心不全、不整脈、狭心症・心筋梗塞などに対する治療法は年々進化し、例えばカテーテルを用いた心臓内の治療、冠動脈ステント留置、植込み型ペースメーカー・除細動器(ICD)など、身体への負担が少なく効果の高い治療が広まりました。
近年では、iPS細胞を用いた再生医療、人工心臓、ロボット支援下の手術といった、まさに「未来医療」の実用化も現実のものとなりつつあります。しかしどれだけ技術が進化しても、心臓が止まれば命は失われます。この事実は変わりません。
健康であることが人生を豊かにする
「人生100年時代」と言われる今、単に長生きするだけでなく、“健康で質の高い生活”をいかに維持できるかがますます重要になっています。
循環器疾患は、症状が進行してから気づかれることが多く、心機能が低下すると、日常動作にも支障が出て、入退院を繰り返す生活になることもあります。さらに、長期の治療には経済的・心理的な負担も伴います。
だからこそ、今のうちから心臓や血管の健康を守ることが、将来の自分の生活の質(QOL)を守ることにつながります。
【図表1】循環器疾患による生活の質(QOL)への影響
| 状態 | QOLへの影響例 |
| 慢性心不全 | 疲労感、息切れ、外出困難、睡眠障害 |
| 不整脈(心房細動など) | 動悸、めまい、集中力低下、脳梗塞のリスク |
| 狭心症・心筋梗塞後 | 再発不安、運動制限、服薬継続の負担 |
| 高血圧 | 無症状でも血管に負担 → 認知機能や腎機能低下 |
医療の主役は「あなた」です
現代医療では、「医師に任せる」「薬だけで治す」という受け身の姿勢では、限界があります。高血圧・脂質異常症・糖尿病といった生活習慣病は、日々の生活の積み重ねによって改善・進行が左右されるからです。
医師は処方やアドバイスを通じて治療をサポートしますが、最も大切なのは患者さん自身の“生活の自己管理”です。
【図表2】循環器疾患を予防・管理する自己管理の柱
| 項目 | 実践のポイント |
| 食事 | 減塩(1日6g未満)、野菜・魚を多く、脂質・糖分控えめ |
| 運動 | ウォーキングなどの有酸素運動を週150分以上 |
| 睡眠 | 6~7時間を目安に、生活リズムを整える |
| ストレス | 深呼吸・趣味・会話などで日常的に発散 |
| 体重管理 | BMI22前後を目標に、体脂肪率もチェック |
| 服薬管理 | 自己判断せず医師の指示通りに継続 |
| 血圧測定 | 毎日朝晩に測定し、記録をつける |
続けるために「目標設定」を
自己管理は簡単ではありません。だからこそ、具体的な数値目標を立てることが継続のコツです。
【実践例】わかりやすい目標設定
- 血圧:収縮期130mmHg未満、拡張期85mmHg未満(日本高血圧学会推奨)
- 体重:BMI22(=標準体重)を目標に
- 運動:1日30分の早歩きを週5日
- 食塩:1日6g未満、加工食品・外食を減らす
医師との「対話」も大切に
医師は、皆さんの体調を見守る伴走者です。疑問や不安、気になる症状、生活の中で実行が難しいことなどは、遠慮せずに医師や看護師に相談してください。
服薬の調整や生活の工夫も含めて、「続けやすい治療計画」を一緒につくっていくことが大切です。
最後に:基本こそが、生涯健康の礎
これまでの回でもお伝えしてきたとおり、
- 自宅で血圧を正しく測定し、記録すること
- 症状や傾向を正しく理解し、早期対応すること
- 薬を医師の指示通り正しく服用すること
- 医療者とのコミュニケーションをしっかり取ること
これらは決して難しいことではありませんが、日々の積み重ねが健康を守る力になります。
“医師任せ”ではなく、“自分ごと”として健康と向き合うことが、100年時代を健やかに生き抜く鍵です。あなた自身が、人生の主役であることをどうか忘れないでください。
参考・引用文献
- 厚生労働省「健康日本21(第二次)」
- 日本循環器学会「循環器疾患予防ガイドライン2022」
- 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2023」
- 国立がん研究センター「人生100年時代の健康戦略」
当院では、下記のような医療サポートを実施しております:
- ・医師によるダイエット薬(GLP-1受容体作動薬など)の処方
- ・漢方専門医による減量指導および漢方処方
- ・管理栄養士による個別栄養指導
- ・鍼灸師によるバイオセラピー
- ・オンライン診療による定期モニタリング
お気軽にご相談ください。
らいふサイエンス内科クリニック 院長 濱屋貢造