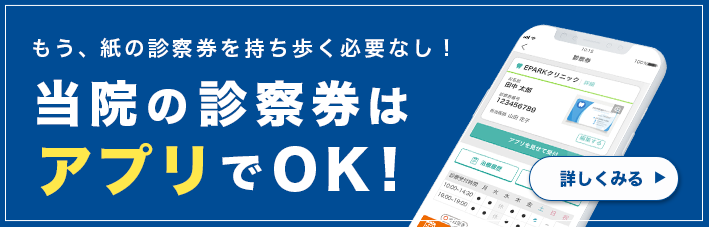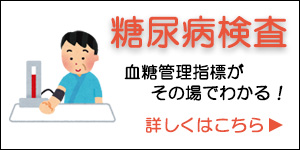BMI判定基準について
肥満の判定には、体重(kg)を身長(m)の二乗で割って算出される「BMI(Body Mass Index:ボディ・マス・インデックス)」という指標が、国際的に広く用いられています。
BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m) という計算式です。
この指標は体格の目安として非常に有用であり、日本国内でも健康診断などで頻繁に活用されています。日本では、BMIが22のときが最も病気にかかりにくい理想的な体格とされており、これを「標準体重」と位置づけています。BMIが25以上の場合は「肥満」、30以上になると「高度肥満」と判定され、さまざまな健康リスクの上昇が懸念されます。
| BMI値 | 判定 |
|---|---|
| ~18.5未満 | 低体重(やせ) |
| 18.5〜24.9 | 普通体重 |
| 25.0〜29.9 | 肥満(1度) |
| 30.0〜34.9 | 肥満(2度) |
| 35.0〜39.9 | 肥満(3度) |
| 40.0以上 | 肥満(4度) |
日本では、BMI22が最も病気にかかりにくいとされる「標準体重」であり、健康を維持する上での目安とされています。
肥満は見た目の問題だけでなく、身体の内側にも深刻な悪影響をもたらします。具体的には、高血圧症、糖尿病、脂質異常症(高コレステロール血症や高トリグリセリド血症など)といった、いわゆる生活習慣病の発症リスクが著しく高くなります。さらに、体重の増加に伴い、膝関節や腰椎にかかる負担も大きくなり、変形性膝関節症や腰痛、椎間板ヘルニアなどの整形外科的疾患も引き起こされやすくなります。
メタボリックシンドロームとの関係
近年では「メタボリックシンドローム(メタボ)」という概念も定着しています。これは、内臓脂肪の蓄積に加えて、血圧、血糖、血中脂質のうち2つ以上に異常がある状態で、以下の診断基準が用いられます。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 腹囲 | 男性85cm以上、女性90cm以上 |
| 血圧 | 130/85mmHg以上 |
| 空腹時血糖値 | 110mg/dL以上 |
| 中性脂肪またはHDL-C | TG≧150mg/dL または HDL-C<40mg/dL |
近年では「メタボリックシンドローム(いわゆる“メタボ”)」という概念も浸透してきました。これは、内臓脂肪型肥満を中心に、高血圧、高血糖、脂質異常という複数のリスク因子が重複することで、動脈硬化性疾患の発症リスクが飛躍的に高まることを意味します。こうした危険な状態は、かつて「死の四重奏」と呼ばれていたほどで、肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症という4つの要因が互いに悪影響を及ぼし合い、血管の内側にプラーク(コレステロールなどの沈着物)が形成されて血管が狭く硬くなる「動脈硬化」を進行させます。その結果、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害といった命に関わる疾患の発症リスクが飛躍的に上昇します。
このような背景からも、日頃から適正体重を意識し、健康的なライフスタイルを確立することは非常に重要です。特に働き盛りの世代や更年期を迎える世代では、体重が少しずつ増加する傾向があり、放置していると数年後には生活習慣病のリスクが高まってしまいます。適正体重を維持するためには、単に痩せればよいというものではなく、体脂肪率や筋肉量にも目を向けながら、無理のない形で体質改善を行っていく必要があります。
とはいえ、短期間で体重を落とそうとするあまり、過度な食事制限や極端な糖質制限を行うことは大変危険です。こうした「無理なダイエット」は、一時的には体重が減少するかもしれませんが、体内の筋肉量まで落ちてしまい基礎代謝が低下します。その結果、食事を元に戻したとたんリバウンドが起こり、以前よりも体脂肪が蓄積されやすい「太りやすく痩せにくい体質」になってしまうのです。
さらに、極端な栄養制限は、エネルギー不足による疲労感や無気力感、集中力の低下、免疫力の低下による感染症のリスク増加、鉄分やビタミン不足による貧血や肌荒れ、生理不順、ホルモンバランスの乱れ、便秘など、身体にさまざまな不調を引き起こす恐れがあります。特に若年女性の間で「やせ志向」が強い場合、将来的な骨粗しょう症や妊娠・出産への影響も心配されます。
適正体重を目指す理由
肥満の予防・改善は、単なる体重減少ではなく、将来の病気の予防や生活の質(QOL)の向上にもつながります。
特に中高年では、サルコペニア肥満(筋肉量が少なく脂肪が多い状態)への対策も重要です。
無理のない健康的なダイエットとは?
「短期間で痩せたい」「すぐに成果が欲しい」といった気持ちから、無理な食事制限に走ってしまう人もいますが、極端なダイエットはリスクが大きく、逆に健康を損ねます。
健康的な減量を目指すには、正しい知識と長期的な視点が不可欠です。まずは現在の自分の体格や体調を把握した上で、現実的な目標を設定し、毎日の食生活を見直しましょう。ポイントは「極端な制限ではなく、継続可能な改善」。バランスの良い栄養摂取(主食・主菜・副菜をそろえること)を意識し、ゆっくりよく噛んで食べること、そして間食や夜食の見直しも大切です。また、ウォーキングやストレッチ、軽い筋力トレーニングなどの適度な運動を取り入れ、基礎代謝を維持・向上させることも有効です。
【無理なダイエットによる主なリスク】
-
筋肉量の減少 → 基礎代謝の低下
-
栄養不足 → 貧血、免疫力低下、集中力低下
-
ホルモンバランスの乱れ → 月経不順、肌荒れ
-
リバウンド → 太りやすい体質に
具体的な生活改善例
健康的に体重を減らすためには、以下のような生活習慣の見直しが重要です。
【食事の工夫】
-
一日3食、主食・主菜・副菜をそろえる
-
炭水化物を極端に減らさず、量と質を調整(白米→雑穀米など)
-
良質なたんぱく質を意識(魚、大豆、鶏むね肉など)
-
野菜は1日350gを目標に(食物繊維・ビタミン補給)
-
間食・夜食・アルコールを控える
【運動の習慣化】
-
週に150分以上の中強度の有酸素運動(例:速歩、サイクリング)
-
毎日少しずつできる筋トレ(スクワット、腹筋、プランクなど)
-
エスカレーターより階段、バス1駅前で降りるなどの活動量UP
【行動の見直し】
-
体重・食事・歩数などを記録し可視化
-
睡眠時間を6~8時間確保(ホルモンバランスの安定)
-
ストレスをためない(ストレス食いを防ぐ)
医師や専門家との連携も重要
すでに高血圧、糖尿病、脂質異常症などの診断を受けている方生活習慣病を指摘されている方や、持病をお持ちの方、内服治療中の方は、自己判断でのダイエットは避け、かかりつけの医師や管理栄養士など専門家と相談しながら取り組むことが重要です。
最近では、医療機関やオンライン診療サービスでも、肥満やメタボ対策に特化した医師による指導や処方、管理栄養士による食事指導などを受けられる環境が整ってきています。ひとりで抱え込まず、必要に応じて専門家の力を借りながら、健康的で持続可能なダイエットに取り組みましょう。
当院では、下記のような医療サポートを実施しております:
- ・医師によるダイエット薬(GLP-1受容体作動薬など)の処方
- ・漢方専門医による減量指導および漢方処方
- ・管理栄養士による個別栄養指導
- ・鍼灸師によるバイオセラピー
- ・オンライン診療による定期モニタリング
お気軽にご相談ください。
らいふサイエンス内科クリニック 院長 濱屋貢造