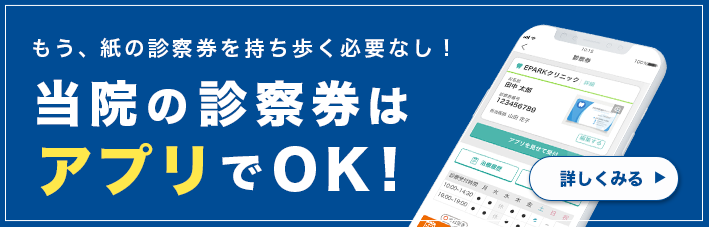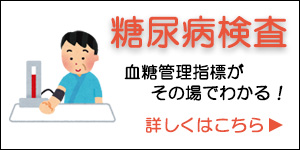循環器の基礎知識 ― 生命を支える心臓と血管のしくみ ―
私たちの体は約37兆個もの細胞が複雑に組み合わさり、組織や臓器をつくっています。呼吸器系・消化器系・神経系・運動器系・泌尿器系など、多くの機能が連携して、生命活動を絶え間なく支えています。
その中でも、循環器系はとくに重要な役割を担っています。酸素と栄養を全身に届け、二酸化炭素や老廃物を回収する「血液の流れ」をつかさどるシステムです。
循環器系の中核を担うのが心臓です。心臓は1日におよそ10万回も拍動し、全身に血液を送り出す強力なポンプです。血液は大動脈から各臓器へと運ばれ、酸素や栄養素を届けながら毛細血管を通って静脈へと戻ります。そして再び心臓へ戻され、肺を経由して新たな酸素を取り込み、再び全身へ送り出されます。このサイクルが「体循環」「肺循環」として機能しています。
【図表1】循環器系の構成と働き
| 構成要素 | 主な役割 |
| 心臓 | 血液を全身に送り出すポンプ |
| 動脈 | 酸素や栄養を運ぶ血管(心臓→組織) |
| 静脈 | 二酸化炭素や老廃物を戻す血管(組織→心臓) |
| 毛細血管 | 酸素と栄養、老廃物の交換を行う最末端の血管 |
循環器の病気とリスク
循環器系の疾患には、以下のような重大なものがあります。
- 狭心症・心筋梗塞(虚血性心疾患)
- 心不全(心臓のポンプ機能低下)
- 弁膜症(心臓の弁がうまく開閉しない)
- 不整脈(心拍リズムの乱れ)
- 動脈硬化、脳卒中、動脈瘤 など
特に心筋梗塞や脳梗塞は、発症後の後遺症や突然死につながるため注意が必要です。これらのリスクは、遺伝や加齢だけでなく、生活習慣病によって大きく高まることが分かっています。
【図表2】循環器疾患の主な危険因子
| 危険因子 | 内容 |
| 高血圧 | 血管に常に高い圧がかかり、動脈硬化が進行 |
| 糖尿病 | 血管内皮が傷つきやすくなり動脈硬化を促進 |
| 脂質異常症 | LDLコレステロールの蓄積により血管が狭窄 |
| 喫煙 | 血管を収縮させ血栓をつくりやすくする |
| 運動不足・肥満 | 代謝異常や血流悪化、心負荷増大 |
| ストレス過多 | 血圧上昇、ホルモンバランスの乱れ |
生活習慣を見直すことで予防は可能です
循環器疾患の多くは、日々の生活習慣の改善により予防・進行抑制が可能です。特に生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症)を早期に発見し、適切な管理を行うことが重要です。
【具体例】今日からできる生活改善習慣
▶ 食生活の見直し
- 減塩を意識する(1日6g未満を目標に)
- 野菜を1日350g以上、果物は200g程度
- 飽和脂肪酸の多い食品(バター、肉脂)を控え、魚や大豆製品を増やす
- 外食時は「小盛り」「汁物を残す」「揚げ物を避ける」
▶ 運動習慣の確立
- 18歳から64歳の方の場合
- 週に合計60分以上の「息がはずみ、汗をかく程度」の運動
- または、毎日30分以上のウォーキングや軽いジョギング
- エレベーターではなく階段を選ぶ
- 週に2〜3回は筋トレやストレッチも取り入れる
▶ その他の生活習慣
- 禁煙(受動喫煙も含めて避ける)
- アルコールは節度を持って(1日1合以内)
- 睡眠は6~7時間を目安に、規則的に
- ストレスは趣味や深呼吸、会話でリリース
健康管理の第一歩は「血圧コントロール」
循環器を守るための最初の一歩は血圧の把握と管理です。家庭での血圧測定を習慣にし、以下の数値を目安に管理しましょう。
【図表3】血圧の分類(日本高血圧学会ガイドラインより)
| 分類 | 収縮期(上) | 拡張期(下) |
| 正常血圧 | ~119 mmHg | ~79 mmHg |
| 正常高値 | 120~129 | ~79 |
| 高値血圧 | 130~139 | 80~89 |
| 高血圧 | 140以上 | 90以上 |
毎日決まった時間(起床後・就寝前)に測定することで、変化に気づきやすくなります。
今後に向けて:心臓を守るための知識を深めましょう
循環器系は、気づかぬうちに病気が進行する「サイレントキラー」が多く、予防と早期発見がとても重要です。自分自身の体の状態に目を向け、「知ること」「測ること」「変えること」を習慣にしていきましょう。
次回は、循環器疾患の最重要因子である「血圧」について、より詳しくお話ししていきます。
参考・引用文献
- 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2023」
- 日本循環器学会「循環器疾患予防実践ガイドライン」
- 厚生労働省 e-ヘルスネット「循環器疾患」「生活習慣病予防」
WHO Cardiovascular diseases fact sheet (2023)
当院では、下記のような医療サポートを実施しております:
- ・医師によるダイエット薬(GLP-1受容体作動薬など)の処方
- ・漢方専門医による減量指導および漢方処方
- ・管理栄養士による個別栄養指導
- ・鍼灸師によるバイオセラピー
- ・オンライン診療による定期モニタリング
お気軽にご相談ください。
らいふサイエンス内科クリニック 院長 濱屋貢造