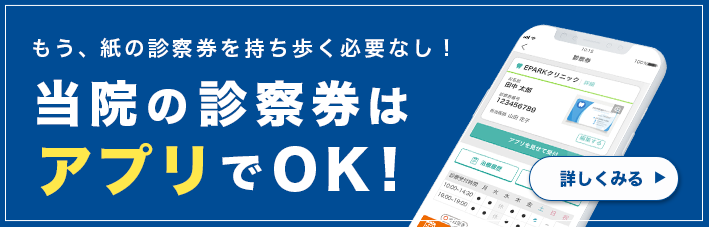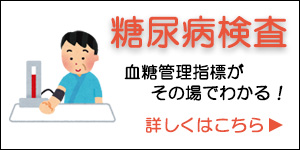お薬はきちんと飲みましょう ―循環器治療における服薬順守の重要性―
病気の治療において、薬の力は非常に重要です。しかし、その効果を正しく引き出すためには、「薬を正しく飲む」こと、つまり服薬順守(ふくやくじゅんしゅ)が欠かせません。
近年では「服薬コンプライアンス」や「アドヒアランス」という言葉も使われており、どちらも医師の指示に従い、処方された薬をきちんと服用することを意味します。ただ薬を「もらう」だけでなく、継続して、正しく、習慣として飲むことが、治療の成功には不可欠なのです。
薬は「出されたとおり」に飲んでこそ効く
医師は、患者さんの体調・年齢・疾患の進行度などを踏まえて、薬の種類・量・飲み方・服用時間を細かく設計しています。特に循環器領域の薬では、心臓や血管、血液の状態に直接関わるため、服薬の精度が治療成績を大きく左右します。
【図表1】循環器疾患で処方される主な薬と目的
| 薬の種類 | 目的・主な効果 |
| 降圧剤 | 血圧を下げて動脈硬化・脳卒中を防ぐ |
| 狭心症治療薬 | 心臓の酸素不足を緩和する(硝酸薬など) |
| 抗不整脈薬 | 心拍のリズムを整える |
| 利尿剤 | 体内の余分な水分を排出し心臓の負担を減らす |
| 抗心不全薬 | 心臓のポンプ機能をサポート |
| 抗血栓薬 | 血栓を予防し、脳梗塞・心筋梗塞を防ぐ |
特に抗血栓薬や抗不整脈薬は、飲み忘れや中断が致命的なリスクを引き起こす可能性があります。
自己判断で薬を止めるのは非常に危険
「今日は調子がいいから薬は休もう」「血圧が下がっているから1錠に減らそう」といった自己判断による調整は厳禁です。血圧や心拍などは一時的に良く見えても、体の中では薬の作用で保たれている状態であり、服薬中止によって急激な血圧上昇やリバウンドが起こり、心筋梗塞や脳卒中を引き起こす危険性があります。
【実例】服薬中断で起きた重篤なケース
70代男性。降圧剤・抗血栓薬を服用中。旅行の間に服薬を忘れ、帰宅後に激しい胸痛と冷や汗を訴えて救急搬送。結果は心筋梗塞。服薬中断が直接の引き金となったと推定。
服薬順守は「患者参加型」の治療スタイルへ
かつては「医師の言うとおりに黙って従う」のが一般的でしたが、現代医療では患者が主体的に治療に参加する「アドヒアランス重視」の姿勢が求められています。
薬の効果や副作用について納得し、食事や運動、睡眠などの生活スタイルに合った服薬スケジュールを立てることが、長期的な服薬継続につながります。
【図表2】服薬順守を高めるための5つのポイント
| 工夫 | 内容 |
| 薬の管理 | お薬カレンダー・ピルケース・アラーム付きアプリを活用 |
| 飲み忘れ対策 | 食事とセットにする、スマホでリマインド |
| 副作用の相談 | 我慢せず医師や薬剤師に伝える |
| 他院受診・サプリの報告 | 相互作用を防ぐために必ず申告 |
| 自己測定と記録 | 血圧や脈拍を毎日記録し、受診時に医師と共有 |
生活と連動した処方設計を
たとえば「朝が忙しく薬を忘れやすい」場合、医師に相談すれば1日1回の長時間作用型の薬に切り替えることも可能です。また、服用中のサプリメントや健康食品(特に血圧・血栓対策を謳うもの)がある場合は、相互作用のリスクがあるため必ず医師に申告してください。
まとめ:服薬は「受け身」ではなく「参加型」に
服薬順守は、単なるルールではなく、命を守る行動です。特に循環器疾患では、飲み忘れ・中断・飲み間違いが、重大な転帰につながることがあります。
日々の生活と連動した無理のない服薬習慣をつくり、医師・薬剤師とよく相談しながら、“自分の治療に主体的に関わる”姿勢を持ちましょう。
それこそが、治療効果を最大限に高める最良の方法です。
参考・引用文献
- 日本循環器学会「循環器病予防ガイドライン2022」
- 厚生労働省 e-ヘルスネット「服薬アドヒアランス」
- 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2023」
- 日本薬剤師会「正しい薬の飲み方ガイド」
当院では、下記のような医療サポートを実施しております:
- ・医師によるダイエット薬(GLP-1受容体作動薬など)の処方
- ・漢方専門医による減量指導および漢方処方
- ・管理栄養士による個別栄養指導
- ・鍼灸師によるバイオセラピー
- ・オンライン診療による定期モニタリング
お気軽にご相談ください。
らいふサイエンス内科クリニック 院長 濱屋貢造